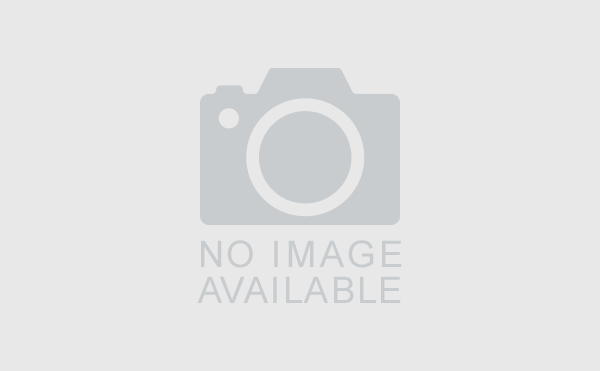漢方と倦怠感について
しっかり睡眠をしても、疲れやだるさが抜けない時があります。
つまり、全身の気が足りなっている状態です。
症状が重く、仕事を休んだり、家の中で寝込んでしまったりする場合もあります。
一般的に内分泌系の異常や精神疾患などの原因となる病気がないのに、
半年以上疲労や倦怠感が続くと、慢性疲労になりがちです。
さらに、病後や手術後に体力が低下して、食欲が落ちて風邪を引きやすくなる事もあります。
目次
漢方と倦怠感について
倦怠感は、過労、睡眠不足、不規則な生活、精神的なストレスの蓄積、
栄養不足などの日常生活から生じる主観的感覚です。
つまり、慢性的な体調不良や病気のサインとして捉えられる事が多いです。
そして気の不足で気虚の状態になると、人参や黄耆などの
気を補う作用がある生薬を含んでいる漢方薬が検討できます。
具体例は、気の巡りが滞った気鬱、血の不足した血虚、
脾の働きが低下した病態などに向いています。
●脾は、五臓の1つです(五臓は、心・脾・肝・肺・腎です)。
消化、吸収、栄養の運搬、血液のコントロールなどの様々な機能に関わっています。
補中益気湯は、元気を補ったり、胃腸の働きを整えて
疲労や食欲不振を改善する効果が期待できる漢方薬です。
主な成分は、人参、黄耆、蒼朮などです。
つまり、体調が悪い時に体力を回復しやすいです。
①気鬱
●加味帰脾湯は、体力の低下、貧血、のぼせ、不眠、精神不安に対応しやすいです。
●加味逍遙散は、怒り、精神不安、倦怠感、不眠、のぼせに対応しやすいです。
●柴胡桂枝乾姜湯は、倦怠感、精神不安、動悸、不眠に対応しやすいです。
②血の不足(血虚です)
●人参養栄湯は、咳、身体衰弱、貧血、動悸、食欲不振に対応しやすいです。
●十全大補湯は、慢性疲労、貧血、身体衰弱、皮膚に艶がない場合に対応しやすいです。
●当帰芍薬散は、血色不良、むくみ、冷え性、目眩、月経不順に対応しやすいです。
●四物湯は、貧血、目眩、皮膚が乾燥してカサカサになる場合に対応しやすいです。
③気虚、脾虚
●人参湯は、疲労、冷え性、下痢、胃もたれ、
唾液が多い場合、尿量が多い場合に対応しやすいです。
●六君子湯は、胃腸虚弱、疲労、食欲不振、食後に眠たくなる場合に対応しやすいです。
●小建中湯は、寒がり、腹痛、虚弱体質、胃腸が弱い場合に対応しやすいです。
④腎虚
●六味丸は、口の渇き、尿量減少、火照り、
頻尿、夜間尿(特に若者です)に対応しやすいです。
●八味地黄丸は、手足の冷え、口の渇き、尿量減少、
頻尿、火照り、腰痛、夜間頻尿に対応しやすいです。
⑤夏バテ
清書益気湯は、食欲不振、倦怠感、胃腸が弱い場合に対応しやすいです。
胃痛・胸やけ・胃もたれの食事療法について
①気の巡りの正常化
ピーマン、タマネギ、シソ、蜜柑、グレープフルーツ、鮭、陳皮、八角などが向いています。
②腎臓の補助と精の生成
キャベツ、ゴボウ、ブドウ、シシャモ、スッポン、栗、豚肉、
鯛、鰻、鶏レバー、鳥骨鶏、牛乳、黒胡麻などが向いています。
③気を補う
カボチャ、シイタケ、牛肉、羊肉、烏骨鶏、
鰻、鰹、芋類、餅米、大豆などが向いています。