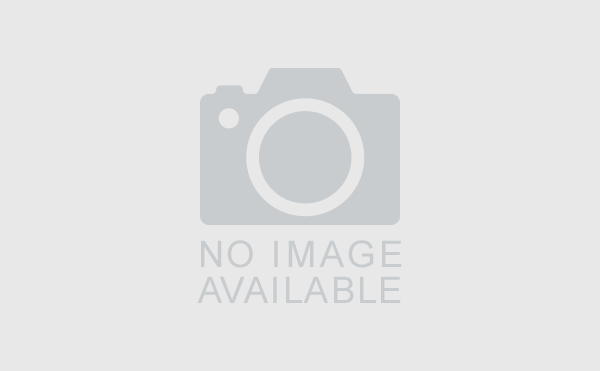発電と送電の仕組みについて
発電した電力は、電気事業者を通じて家庭、公共施設、店舗、オフィスビルなどに届けられます。
エネルギーを生み出す装置は、どのような種類があるのでしょうか?
日本の発電方法はたくさんあります。
現在は、火力発電、水力発電、原子力発電が主流です。
目次
①日本の電源別発電電力量構成比について
日本電源別発電電力量構成比の大きなシェア率を誇っているのが火力発電(全体の約9割です)です。
2011年03月11日、東日本大震災の影響により多くの原子力発電所の稼働が停止しています。
原子力発電に頼ってきたエネルギーを補う為に火力発電の規模が大きくなりました。
さらに、枯渇性エネルギーの使用量が高いです。
天然ガス、石炭、石油の順に使われています。
再生エネルギーのシェア率は微粒です。
ちなみに水力発電は大規模なダム建設による発電方法なので、
再生エネルギー枠には当てはまらないです。
水力発電(再生可能エネルギーです)の法律上の定義は、3万kW(ワットです)未満の中小規模です。
②発電と送電の仕組みについて
色んな種類によって発電された電力は、送電線を通じて一般家庭などに送られます。
しかし、送電線を流れている電力の一部は電気抵抗により熱エネルギーに変換して失われます。
電圧が高いほど抵抗は小さくなります。
送電線は、高圧の電流が流れるようになっています。
高電圧が居住地付近に存在すると危険だと思います。
そこで、変電所が設置されました。
変電所は変電をして、一般家庭向けに送られる仕組みになっています(高電圧を落とす作業です)。
ちなみに電気は、基本的に貯める事ができません。
●電線抵抗…物質が電気を流れにくくする事です。
抵抗が大きいほど、多くの電気が熱エネルギーに転換されて、発熱量も多くなります。
金属は抵抗が少なく、電気を通りやすいです。
非金属は抵抗が大きく、電気を通しにくいです。
●熱エネルギー…物体の内部エネルギーの事です。
さらに、物体を構成する原子や分子の熱運動エネルギーとも呼ばれます。
具体例は、コンビニにある電子レンジです。
コンビエンストア商品を加熱して、温める事ができますね。
送電網ネットワークを管理している一般電気事業者は、発電所の家電状況をコントロールしています。
そして、同時同量の原則が適用されています。
同時同量原則は送電網ネットワーク内に発電される電力量と消費用電力量は、
常に一定の範囲内で需要と供給のバランスを保つ事です。
再生可能エネルギーの場合は、同時同量の原則が難しいです。
気候変動によるリスクなどにより発電量のコントロールが問題視されています。
再生可能エネルギーの普及するためには、大きな課題を改良していく必要性があると思いました。