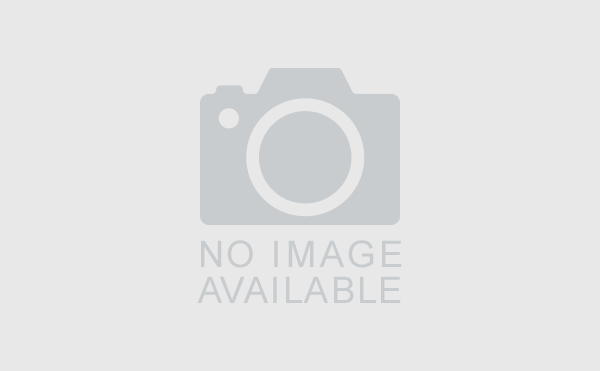診療情報提供書について
開業医から病院へ、病院から在宅診療所へなどの医師が他の医療機関を紹介する事が増えています。
そして患者さんは、紹介状を持って紹介先の医療機関を受診すると、
大学病院でも初診時特定療養費はかからないです。
つまり、患者さん病気や状態に合った適切な医療を受ける事が可能です。
一般的に紹介状は、診療情報提供書です。
さらに初診時特定療養費(選定療養費です)は、紹介状なしに200床以上の病院を
初めて受診する際に、通常の医療費ではない患者さんが負担する費用です。
目次
診療情報提供書について
診療情報提供書は、基本的に封しています。
患者本人であっても、宛先以外の人が開封する事は望ましくないです。
そして宛先は、紹介状を書く医師が決めます。
医療機関名と診療料までが書かれている場合や
医師の名前まで指定されている場合などもあります。
さらに地域の中核病院は、在宅診療向けセンターを設置している事があります。
病院と診療所の連携をスムーズにしています。
医療機関は、診療所が通院治療、病院が入院治療、大学病院が高度な治療を提供しています。
しかし、風邪や日常的な病気で大学病院に行く人が増加すると、
外来診療が混雑してしまいます。
つまり、必要な患者さんに高度な医療を提供できなくなってしまう恐れがあります。
非効率や弊害を未然に防ぐ為に、紹介状の活用をする事で対応できます。
結果的に、医療機関の連携が支えになります。
医療機関の紹介が国から推奨されています。
病院や診療所の役割の違いで診療科の専門性が充実しました。
そして紹介状は、患者名、性別、病気の経過、治療の履歴などの
今後の診断と治療に必要な情報が抜粋して記載れています。
さらにCTやX線などの検査画像がある場合は、
病気の現状がより正確に分かりやすくなります。
診療情報提供書の発行の条件について
①専門範囲を超えた場合
最初に診断した医師の専門領域を
検査を経て専門が異なるとして判断された場合に有効です。
具体例は、患者さんが胃潰瘍を疑って内科を受診して、
調べた結果癌の疑いも発覚した時です。
結果的に癌診療連携拠点病院を紹介される事があります。
つまり、内科☞紹介状☞整形外科☞紹介状☞心臓外科です。
②医療機関に備わった機能で患者さんの治療に対応できない場合
機能が不十分な場合に有効です。
具体例は、開業医で手術の設備が不十分な場合や
病院から退院する際に患者さんの居住地の在宅医療を確保したい場合などです。
つまり、診療所で検査設備が不十分☞紹介状☞病院で手術設備が不十分☞紹介状☞総合病院です。
③治療ステージに応じた医療機関を紹介する場合
病状が不安定な急性期を脱して、リハビリステーション病院に移る場合に有効です。
つまり、急性期☞紹介状☞回復期、亜急性期☞紹介状☞慢性期です。